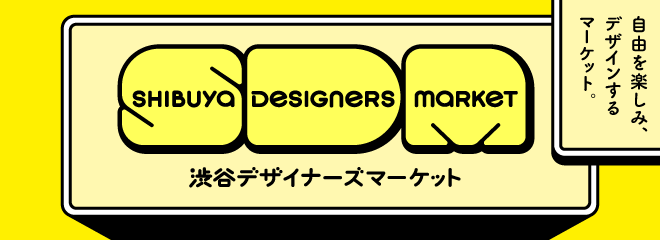ジャーナル
「13F/OLDNEWS」というつながり続ける紙片

世界の生活者が記者となって〈私的エポックメイキング〉を伝える新聞「13F/OLDNEWS」(以下「13F」)。渋谷キャスト、渋谷ヒカリエ、渋谷スクランブルスクエアをはじめ、キャットストリートのコーヒースタンド やショップなど、渋谷を中心に各所で配布されています。
「13F」は2021年10月、装幀家の緒方修一さんが編集長となり、作家の伊勢華子さんと創刊したブランケットサイズの新聞。イラストが大胆に採用された紙面には、世界の多様な都市、僻地で暮らす人の日々流れては消えていく機微や葛藤があふれています。出逢うはずのない誰かのふとした瞬間に、新聞を手にした人は自分を垣間見ることができます。
毎号、配布開始後すぐになくなってしまい、タイミングを逃すと手に入れることも難しくなっています。
2023年で創刊から2年、日夜制作に取り組む「13F」編集室ではどのような思いで各地から届く声と対峙しているのでしょうか。なぜ渋谷を発信源に、世界の都市や僻地を結び、それを新聞という紙にこだわり刊行を続けるのでしょうか。
発行人の伊勢華子さんにうかがいました。
【プロフィール】
伊勢 華子
作家。著書に、競輪学校女子一期生の汗と涙を描いた「健脚商売」(中央公論)「たからものって何ですか」(パロル舎)「ひとつのせかいちず」(扶桑社)「サンカクノニホン-6852の日本島物語-」(ポプラ社)など。
このほかの活動に「Kinki Kids」への作詞提供、浅草東洋館でのバナナの叩き売り、渋谷のラジオ毎月第一月曜『シフにぃ』でパーソナリティなど。
PHOTOGRAPHS BY Yuka IKENOYA(YUKAI)
TEXT BY Atsumi MIZUNO
とるにたらない事件。細部にこそ宿るものがある
伊勢:「13F」の刊行を考えたのはコロナ禍の2021年、日もまだ昇らない明け方、渋谷キャスト13Fの一室から巨大なビル群を眺めていた時です。ビルだけでもたくさんあるのに、そのひとつずつにさらに無数の窓がある。もうすぐ夜明けだというのにいくつもの窓が煌々としていて、その中のひとつに自動販売機のボタンを押す男の人が見えました。紙コップの飲み物をすするその人は今、どんなことを思っているのかを知りたかったですね。
同時に、かつて日本に6852ある島々の絵本をたずね歩いてつくった記憶が蘇りました。どんなちいさな島にも行くことができるけれど、向かいの窓のあの人に会えない。話せない。どうしたらあの人の心のなかに飛んでいけるのか。これが私的エポックメイキング「13F」刊行の源です。
遠くは、地球の裏にいる誰かかもしれないし、電車で隣に座る誰かかもしれないけれど、あの明け方に見た光景、互いに大きな窓で開かれているけれど、ここから見えるあの人に私が話しかけることはできない。これだけSNSで人と人がつながっているけど、1本道を挟んだ向かいのあの人と会う術はない。何かとても窮屈に感じました。
新聞名「13F」は、巨大迷路のような都市・渋谷、そのなかの小さな一室から発する機微が、遠い街のどこか、遠い窓の向こうの機微と出逢えることができたらという思いで編集長の緒方修一が名付けました。サブタイトル「OLDNEWS」は、記憶とともに生きる私たちにとって何が今で、何が昔か。何が新しく、何が古いは曖昧で、複雑に入り混じるからです。

伊勢:創刊準備vol.0制作時、渋谷という街、渋谷キャストという商業施設で刊行する初の紙媒体なら、施設のショップや渋谷で活躍する人をフィーチャーするのかと思ったという声もありました。でも私や編集長の緒方は、渋谷ももっとみんなのものというか、世界を代表する都市、開発真っ只中の渋谷から、世界に同じようにある都市をつなげられたらと考えました。
こんなこと感じているのは自分だけだと思っていたものをどこかの誰かが同じように思っている。そんなふうにひとつの感情を見るにしても、ひとつの渋谷という街を見るにしても、一回地球の裏側に行った上で見てみたい。書かれているものは、とるに足らない事件です。でも侮れない。そんな細部にこそ宿るものがあるからだと思います。
配布は渋谷を拠点に行っていますが、書いてくれたひとりひとりが特派員となり、毎号NYやベルリン、ソウルなどでも配布してくれています。編集室には朝起きると、各地で記事を読んだ人の声が飛び込んできますし、寝ようと思う頃に仕事を開始する都市の人からの原稿が届く。入稿時はもう寝れないですよね。
そういった編集室のバックヤードをそのままオープンしてしまおうと、Instagram「M13F」を発信しています。デパートなんかで1Fと2Fの間のちょっとしたスペースがあって中2Fと呼ばれてますけど、同様で「13F」が生まれる少し手前、12Fと13Fの間といった感じです。

伊勢:機微というか、人の気持ちがほんの少し揺れる瞬間が好きです。次々、浮び上がっては消えていく機微を書くことで留めることができる。もちろん流れて消えることは悪いことでもなく、そういうものだと思うんですが、その人の中で消えてなくなってしまうことものを書き留めることで、何年か後の自分に届けることもできる。また、それを受け取った別の誰かがいつもの帰り道に違う方に曲がりたくなったりする。
私が社会に出て最初に刊行したのは、世界24の国と地域を巡って出会った子どもたちに描いてもらった宝物の絵を集めた絵本ですが、それは「13F」でやっていることと少しつながっているかもしれないと思うことが最近あります。この広い日本や世界にピンポイントで針を落とし、その人の声を聞く。その人のちょっとした揺らぎや沈黙をすくい上げる。

「子どもの心はどんなだろう」という想いから、画用紙と24色のサインペンを手に世界をめぐり、
出逢った119人の子どもたちに「たからもの」の絵とエッセイがつまった絵本
『「たからもの」って何ですか』(パロル舎)。
同じく「せかいちず」の絵を描いてもらい製作した『ひとつのせかいちず』(扶桑社)
伊勢:2022年冬刊行vol.5の巻頭は、創刊から寄稿してくれているソウルの友人が、いつものテニスの帰り道に梨泰院の惨事と遭遇する瞬間を書いてくれています。あってはならない出来事が私たちの日常に起こる。記事を目の当たりにすると、生と死、肥大化したものとか弱いもの、笑みと涙、そうしたものが薄紙一枚すれすれ、背中合わせにあることを突きつけられます。
編集方針は、非編集
伊勢:編集長の緒方が当初から徹底している方針は、非編集であるということです。漢字などの文字統一も書き手ごとに違います。私も受け取った原稿を読んでいると気になるところもでてきますが、言葉の使い方、句読点などはその人の癖がありますよね。でも編集するとだんだん私っぽくなってしまうので、どうしてもわからないところや、明らかに間違えているところ以外はそのままです。
新聞が刷り上がったら郵便は使わず、自ら届けに行きます。渋谷キャストも、渋谷ヒカリエも従業員や配達員の入口、通路は一般とは別にあって迷路のようになっているので、行ったからといってスッとは渡せません。でも現地から連絡するとみなさん出てきてくれて、ああどうも、となるわけです。
束になった紙だから運ぶのはすごく重いです。いろいろ試した結果、頭に乗せるのが一番安定しますね。まさにアフリカやインドで頭に水を乗せて運ぶ女性たちに行き着くわけですが、刷り上がりほやほやの新聞と渋谷を歩くのは清々しいです。
 「13F」が自分の手を離れ、ほかの人の視点で解釈されて定義づけられるのもまた面白い、と話す。
「13F」が自分の手を離れ、ほかの人の視点で解釈されて定義づけられるのもまた面白い、と話す。
私的エポックメイキング
伊勢:イベントも開催しています。想像を遥かに超えて盛況です。2022年9月には、2020年に逝去された歌人の岡井隆さんの遺言のような文で編まれた珠玉の新刊「岡井隆の忘れもの」(書肆侃侃房)にあわせてトークセッションを開催しました。編集長の緒方は装丁家でもありますが、彼が゙常々語る「何でもない装丁」と題して、ともに本のアートワークを手掛けた谷山彩子さんをお迎えしました。
装丁と装画という両極の姿勢を紐解く60分でしたが「喫茶店でおしゃべりする2人の話を偶然隣の席で聞いてしまったような距離感だった」。「ありそうでない本の話を聞いてしまった」。など開催後たくさんのコメントをいただきました。
同年12月は、+ Nibroll (ニブロール)の回遊型パフォーマンス「距離のない旅」の公演を終えたばかりの矢内原美邦さんをお招きしました。矢内原さんは古くからの知人でもありますが、彼女が今何を見て、どんな場所に立っているか紐解きたくて場をもちました。


伊勢:彼女と最後に話したとき、私は彼女に伝えそびれていたことがあって、でも時間が経つうちに伝えるものが何かを忘れてしまって、伝えたいことがあったという輪郭だけが残ってしまったのもあり彼女と話す45分に「あの時のあ」と名付けました。岸田國士戯曲賞事務局長で、矢内原さんの著書「前向き!タイモン」を刊行する白水社の編集者・和久田賴男さんも登壇くださり、聞き手の私は冬の大三角形を描くように観客に混じるかたちで着席しましたが、その場に居合わせた36人に何かが突き刺さるものがありました。
それが何かは、容易に言葉にすることを許さないものでしたが、帰り道には各自が持ち帰ったものを感じていたと思いますし、私自身、それは今も残っていて支えられている節がありますね。
伊勢:12月は目白押しで、その翌週には「目に映る、意味のわからない途中を生きている」と題して、写真家・朝岡英輔×装丁家・緒方修一でトークセッションを行いました。朝岡さんが刊行した写真集「over」の秘話にはじまり、緒方が装丁を手掛けた沢木耕太郎さん新刊「天路の旅人」に至るまで厚みのあるトークでしたが、沢木さんの本は年明けにNHKで特番インタビューがあったので、来場者の方から「一冊の本を作家と装丁家の両面から聞けるなんて思いもよらなかった」と多数のメッセージをいただきました。 私的エポックメイキングといいますか、自分を主語に語ると見えてくるものが必ずありますよね。それを逃したくないと思います。
紙にこだわるのはどうしてでしょう。自分に体があることに似ているかもしれません。体がなくなっても魂はなくならないように、書いたものは紙がなくなっても生き続けるでしょうね。恐いくらいあらゆる場所で。
新聞を刊行し続けることは「13F」を手にしてくれている人への約束だと思っています。私は「健脚商売」(中央公論社)という競輪界に女子一期生として飛び込んだ女の子たちの本を書いたことがあるんですが、競輪って日本のどこかで365日開催していて、盆正月も関係なく、必ずどこかで誰かが走っているんです。そんなふうに必ずいてくれる、必ずあるということは不安定で先の見えない時代にとても重要だと思っています。
 渋谷キャスト広場の大階段。ここを紙面にするという。
渋谷キャスト広場の大階段。ここを紙面にするという。
伊勢:次に考えていることもあります。渋谷キャスト1Fにある大階段そのものを紙面にして号外を出せないか。道行く人の声を文字にしてそのまま階段に投影できないか。そんなことを思っています。
そこに集まったものをひとつに束ねた時、それこそ今の渋谷の姿が浮かび上がるのではないかと思います。
 「何でもない本」「あの時の「あ」」「目に映るみんな、
「何でもない本」「あの時の「あ」」「目に映るみんな、
意味のわからない「途中」を生きている」と、3回のイベントを開催した。
新聞の根底に流れる小さな葛藤についてもイベントで触れていった。
世界を代表する都市・渋谷から、世界の都市をつなぐ「13F/OLDNEWS」。
伊勢さんは最後に言いました。「つなぐといっても、もともとはあったものなんですよね。それが時代によって散り散りになってしまった。だからそれを『13F』という紙片に私たちは集めているんだと思います」。
時代によって散り散りになった人の機微が紙の上に集まる。それが束となる時、私たちの窓にはどんな景色が広がるのでしょうか。