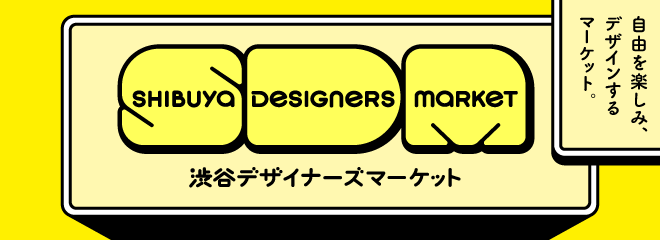ジャーナル
【ALL THE WORLD'S A STAGE -劇場の本質を、いま考える-】
「もう一度やり直す」という覚悟でつくる2030年の劇場モデル

日本で最も歴史の長い「劇場プロデュース企業」として、全国250カ所以上の劇場計画に携わり、劇場を中心としたまちづくりにも長年取り組んでいる(株)シアターワークショップ。 渋谷キャストの開業当初から多目的スペースと広場の運営を担い、「アーバンカタリスト」シリーズをはじめ、多くのエリアマネジメント企画を手がけてきました。
新型コロナウイルスの影響で、演劇やライブといったエンタメが深刻な影響を受ける中、同社は渋谷キャストを拠点に新たな挑戦を始めました。 それが、国内外の劇場関係者と共に、次世代型の劇場のあり方を考える「劇場セミナー」です。去る8月6日にオンライン配信されたキックオフでは、イントロダクションとして同社代表の伊東正示さんが、 劇場を取り巻く現状や課題、2030年に向けた劇場づくりの論点を挙げ、約400名の参加者に問題提起しました。
変化の渦中にあって、劇場セミナーを行う先にどんな未来を見ているのでしょうか。今感じている課題やこれからの劇場やエンタメの向かう先について、伊東さんに加え、劇場セミナーの運営に関わる小林徹也さん、小池浩子さん、丸山健史さんに話を伺いました。
【プロフィール】
伊東正示/株式会社シアターワークショップ、代表取締役
早稲田大学理工学部建築学科卒。同大学院で劇場・ホールについて研究。在籍中より文化庁(仮称)第二国立劇場設立準備室の非常勤調査員として活動。 1983年、香川県県民ホールの計画を機にシアターワークショップ設立。2008年日本建築学会賞(業績)受賞。一般社団法人日本建築学会、公益社団法人日本建築家協会会員。
劇場演出空間技術協会(JATET)理事。劇場芸術国際組織(OISTAT)日本センター副会長、建築・技術委員会委員長。
小林徹也/事業開発室 マネージャー
早稲田大学理工学部、同大学院で建築学を専攻。大学院時代に劇場ゼミを開催し早稲田大学坪内博士記念演劇博物館の旧帝国劇場の模型の研究製作を行った。また早大ミュージカル研究会の音楽監督を務め、商業系劇場でアルバイトをしながら欧米の劇場を巡る。 劇場建築追求のためシアターワークショップ入社。多くのプロジェクトにハード担当として参画。渋谷ヒカリエホールの自主事業ではBGM作曲を手がけている。
小池浩子/事業開発室 マネージャー
早稲田大学第二文学部表現芸術系専修に在学中に、映画館でのアルバイトを経験。代表である伊東氏が講師を務めた早稲田大学の劇場人養成コースの一期生として劇場でのインターンを経験し、シアターワークショップに入社。
ワークショップなどを通じた地域劇場の立ち上げのみならず、民間プロジェクトでも活躍。平成27年度文化庁新進芸術家海外研修制度研修員。
丸山健史/施設運営部 執行役員
早稲田大学第二文学部卒業後、映像制作会社に就職。宣伝部に所属し、雑誌、ラジオやテレビ番組など多様な媒体の立上げに関わり、イベントのプロジェクトにも携わる。 その後、文化エンタテインメント担当として都市開発プロジェクトに参加した後、渋谷ヒカリエの開業を機に、シアターワークショップに入社。施設運営部門の発足時から統括マネージャーとして活動中。
PHOTOGRAPHS BY Yuka IKENOYA(YUKAI)
TEXT BY Atsumi NAKAZATO
なんでも劇場、すべてが劇場、世界が劇場。劇場を広く捉えることで生まれる未来
ーーそもそも劇場セミナーは、どういう思いからスタートしたのでしょうか。
小池:2030年、近未来の劇場の姿はどうなるのか。この大きな問いを自分たちだけでなく、劇場に関わる人たちと一緒に考えたいという思いから、全5回のセミナーを始めました。次の10年に向けて伏線を張って、10年かけて回収していくことが目標です。
丸山:元々劇場セミナーはリアルな場でやりたいと考えていました。でもコロナの影響でそれができなくなり、渋谷キャストの多目的スペースを使ったオンライン配信へと振り切った時、せっかくやるならオンラインの可能性を追求して、オンライン配信のベストモデルをつくりたいという思いもありました。それだけでなく、エンタテインメントシティである渋谷で、劇場の未来を語ること自体にすごく意味があるんじゃないかなと思っています。
伊東:僕らのような劇場や演劇に関わる者にとって、やはりコロナの影響というのはすごく大きいです。演劇は、演じる人と観る人がリアルな空間の中で対峙することで成立するものですが、それが禁じられているというのは大変な状況なんですね。この状況をどう切り抜けて新しいあり方を見出していくのか、いろんな工夫がされている中で、同時配信や無観客ライブといった映像技術を使った方法がどんどん起こってきています。
それを否定的に捉えるのか、むしろ新しいアート作品が生まれるチャンスだと肯定的に捉えるのかというところが大きな分かれ道ですが、当然僕らは最新技術をどう活かしていくのかを考えています。その一つが、今回の劇場セミナーです。
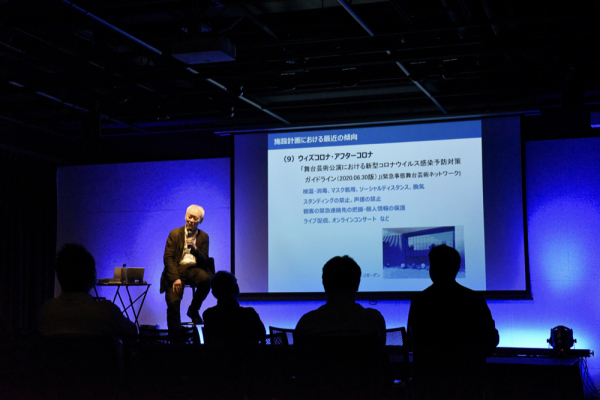
小池:キックオフに参加されたのは、ディベロッパーをはじめ、劇場の運営者、劇場設備の技術者など、みなさん劇場に関わる方々で、約400名とリアルなセミナーの参加者をはるかに上回りました。それも東京だけなく地方、そして海外と国内外からご参加いただき、終了後はリアルなセミナーに引けをとらないほど多くのレスポンスもいただけて、オンライン配信の可能性を感じました。
ーー劇場セミナーでは、参加者同士の交流も目的とされているそうですね。
小林:セミナー自体は、これから開発、建築、運営といったカテゴリーごとに行っていきますが、最終的には、参加者のみなさんが分野を超えて議論できるような会を設けたいと思っています。
小池:一方通行のセミナーではなく、劇場のある街の将来を参加者のみなさんで考えていただけるような場を持てたらなという思いもありますね。
伊東:元々「劇場セミナー」というのは、僕が大学時代に学内で始めたセミナーの名称です。その中で、プロとして活躍されている方々をお呼びしたり、幅広くいろんな方々と劇場の未来を一緒に考えてきたことが僕の原体験としてあります。 会社を始めてからも、たくさんの方々にお力添えをいただいてきたので、今後この会社をどう発展させていくのかを考えた時に、自分たちだけではなく、新たにいろんなつながりを持っていきたいと考えました。
ーーオンラインの場を活用することで、渋谷から全国、世界と交流の幅は大きく広がりそうですね。
小池:今回参加されたのは地方の方々がすごく多かったので、都市に寄った話だけでなく、地方に寄り添った話も大事にしていきたいと思っています。というのも、私たちの会社は渋谷にあるんですが、コロナ前は毎日のように地方に出張していて、地方の劇場を取り巻く状況については日々感じるところがあったんです。今は気軽に足を運ぶことができない中で逆に想いを寄せる部分もあって。 今私たちの軸足がほぼ渋谷にある状態の中で、何ができるのかを考えたいんですよね。

小林:どの地域にも、同じような計画で同じような劇場ができてしまいがちですが、私たちは地域の方々と議論しながら、地域のオリジナルの劇場をつくることをめざしてきました。 そんな地域に特化したものが都会にフィードバックされたら、もっとおもしろいことができるかもしれないと思ったりするんです。都市と地方を行き来することで、新たな可能性やチャンスが見えてくることもありますね。
小池:いろんな地方に行って、ホームとして戻るのが渋谷で、地方とのギャップを鮮明に感じられるという意味では、渋谷に会社があることはすごく意味があるのかなと思います。渋谷よりも地方の方がいいなと感じることもたくさんあるので、画一的に渋谷を日本中に広げたいとはまったく思っていなくて、お互いにフラットな感覚で、いろんな知識をそれぞれが持ち寄って話ができるようになればいいなと思っています。
小林:渋谷は現在進行形で新しいものがある一方で、何をやるにもお金がかかりますが、地方にたくさん足を運んでいると、豊かさの定義を揺るがされることが多々あるんです。そんな価値観を覆されるような地方のよさを渋谷に活かせるといいですよね。
小池:東京の人たちって、みんな地方から来ているじゃないですか。なので、私たちが渋谷と地方を行き来して得た感覚を、渋谷にも活かせるんじゃないかなという気持ちもありますね。
ーー御社は、劇場をつくるだけでなく「劇場を中心としたまちづくり」に力を入れていますが、劇場という場をどう捉えているのでしょうか。
伊東:劇場という言葉を聞くと、多くの人は「オペラやバレエを観る場所」とまずは考えると思います。でも実はもっともっと幅広いんですよね。僕は演じる人がいて観る人がいる場所が劇場になると定義していますが、コミュニケーションの一つの手段という言い方をされることもある。目的を絞り込んですごく尖ったものを考える方向もあるけど、僕らはもっと広く考えて、「なんでも劇場、すべてが劇場、世界が劇場」だと捉えています。劇場というものを狭く捉えない方が、ずっと楽しいしおもしろいし可能性が広がるだろうと思っているんです。劇場セミナーでも、自分たちの軸足である演劇や劇場にこだわりながら、もう一本の足はできるだけ遠くまで伸ばして、いろんな人たちとつながっていきたいですね。

小池:オーセンティックな劇場をつくり続けていくという選択もあったのかもしれませんが、時代が変化し、新しいものが劇場の内外で生まれて、未来の劇場の形を考える私たち自身も成長し続けている中で、劇場を中心としたまちづくりに舵を切ったのは、自然の流れだったのかもしれません。
伊東:私たちは創業当初から渋谷を拠点にしてきて、まずはここでいろんなものを生み出して、それを全国に広げてきました。ここでできることはきっと地方でもできると思うんです。何より実験的なことを思い切ってやれるのが、渋谷という街の魅力であり、渋谷キャストの運営母体である東急さんのおかげでもある。劇場セミナーも、劇場に関わる人たちが自由に議論し、新しい展開が生まれるような「実験的な場」になるとうれしいですね。
時代とともに進化の途上。新たな日常にフィットするスペースの形とは
ーーキックオフでは、「近年全国的に劇場の新設や改修が進行している」というお話がありました。これにはどういう背景があるのでしょうか。
伊東:東日本大震災の際、川崎のホールで客席の天井が落下した事故がきっかけとなり、全国的に改修が進められているのが一つと、建設されてから50年近く経つホールが多いので、ちょうど建て替えの時期でもあるんです。さらに近年、地方都市の複合開発で、地域の活性化を目的に劇場をつくるという動きが加速しています。
小林:今や「一開発に一劇場」と言っても過言ではないですね。
ーーそんな中、渋谷の劇場やイベントスペースは今どういう状況にありますか?
丸山:渋谷の中でも特に青山エリアは、非常に多くの劇場やイベントスペースができていて、各会場ともかなり工夫が求められるかなという気がしています。
ーーそれだけ数が増えている中、渋谷キャストの多目的スペースや広場は今どんな状況なのでしょうか。
伊東:建設段階から参加させてもらったのですが、多目的スペースでは多目的に運営するために必要な備品を収納できるようなスペースを確保したり、マイクを通した声が聞き取りやすくなるように音響を高いレベルで調整したりと、使い勝手の面で工夫を凝らしました。今回のキックオフでこのスペースを自分たちで使ってみて、改めて「すごくいい空間をつくったな」と感じました。
広場は小規模なのですが、そのスケール感をどう活かしていくのか、まだまだ試行錯誤の段階ですね。運営担当の丸山さん、どうですか?
丸山:広場というのは日常の状況が大事だと思っていて、その点、平日のお昼時に出店してくださるキッチンカーは多くの人に利用され、日常的ににぎわいが生まれています。そんな日常の光景を多目的スペースでもつくろうと、平日のお昼から夕方の時間帯に「Ping Pong Cast.」と題して卓球場を始めました。これがかなり人気で、リピーターがすぐに付き、近隣の人たちが卓球に興じているという光景が生まれました。
今後はこのスペースを集客型のイベントだけでなく、「オンライン配信の拠点」にしようという考えもあります。イベントスペースや広場というのは、時代や街の状況に合わせて変化していくことが大事なので、ここからどんどん新しい形へと成長させていきたいと思っています。

伊東:これから渋谷には広場空間がどんどんできていくようですね。広場の活用もこれからもっと考えられてきますし、私たちも考えないといけないところです。
小池:渋谷を核にして青山、原宿、恵比寿へと開発が広がり、回遊性が生まれる中で、各エリアの要となる広場で何ができるのかが、エリアの活性化の意味でも重要になってきますよね。
ーー渋谷キャストの広場でやってみたいことや、思い描く構想はありますか?
小池:私は文化庁の派遣で、カナダのモントリオールに一年間住んでいたことがあるんですが、モントリオールは、一年中街なかでイベントをやっていて、まさにフェスティバルシティ。日常にワクワクが同居したような感覚は、クリエイティブの発信地である渋谷だからこそ、取り入れられるものがあるなと思うんです。
例えば、渋谷キャストのco-labに入居されている「Moment Factory」は、モントリオールに拠点を置くマルチメディアスタジオですが、彼らは世界中でいろんなプロジェクトに関わっています。これまでモントリオールのエンタテインメント集団といえばシルク・ド・ソレイユでしたが、今ではそこに名を連ねるほどの存在感を示しています。モントリオールでは、最新の映像技術を駆使した演出が劇場だけでなく、どんどん街に出てきていてすごくおもしろいんですよね。
伊東:映像を使った演出というのは、アートと技術が合わさってつくられますが、日本のものは、アートよりも技術の方が強いことが多いんです。でも彼らの演出は、どちらかというとアートが強い。それも「こんなことができたら楽しいよね」という純粋な思いから始まっているんです。そんな子ども心をすごく大事にしているところが素敵なんですよね。

舞台と観客が一体となれる「リアルな場」の可能性
ーーコロナの影響で、劇場やホールは深刻な打撃を受けていますが、今感じている課題や変化について教えてください。
小池:目先のリアルな問題としては、実際にイベントの数が減る中、弊社の劇場運営を担うチームが日々不安な状態で過ごしているのを間近で見ているので、苦しい状況を肌で感じている部分はあります。観客の目線では、まだ両隣にお客さんがいない劇場に慣れることはできませんが、また満員の劇場で観たいという思いを持っています。
こうした状況を今私たちは初めて体験していますが、100年ほど前にスペイン風邪が流行したときも、劇場は世界で封鎖され、時間を経て再開しました。劇場で観ることの醍醐味って、ただストーリーを観るだけではなく、空気が張り詰めたり緩んだりというのを他のお客さんと一緒に体験できることだと思うんです。やはり今も「劇場で観たい」人はたくさんいるはずなので、コロナが収束すれば元のような状態に戻ると思っています。
一方、こういう危機はまた来るかもしれないということを視野に入れて、ハードとソフトの両面から新しい劇場の形を考えているところです。まだ答えはないんですけれども。
小林:大人数で集まれないという状況に対して、「集まりたい」という意識が今すごく高まりつつあって、コロナが収束した時に劇場はV字回復になるような気がしています。以前の状態に戻った時にどう対応できるのかを今考えておく必要がありますね。
もう一つ考えているのは、「実際に会うことの良さをもっと追求しよう」という流れが生まれるかもしれないということ。通常の劇場には舞台と客席を区切るプロセニアムアーチがありますが、それを取っ払うことで、より観客と演者が一体となって、そこでしかできない体験を共有できる。そんなリアルな体験の魅力が広く認識されるようになった時、日本の劇場は変わっていくだろうと思うんです。
観客と演者が近い距離感で同じ空間を共有してきた小劇場の形態が、中規模から大規模にまで派生していくような気がしています。

伊東:二人とも「戻る」という言葉を使いましたけど、戻ってくる日常は以前のものとは変わっていて、新しくなっていく。時代とともに変わっていくものじゃないですか。この変化の中で、演劇の本質は何なのかをもう一度考え直さなくてはいけない。
いろんな要素を削ぎ落としていった時に最後に残るのは何なのか。演劇でしかできないこと、演劇にこだわらないといけないことって一体何でしょうか。僕もまだ答えは出ていないんだけど、その本質を見出して培養しながら広げていく、つまり、「もう一回やり直せ」ということなんじゃないかなと思っています。すごろくの振り出しに戻ったような感じで、またここから頑張って「あがり」をめざしていきます。

ーー最後に、伊東さんがめざす、これからの劇場とはどんなものでしょうか。
伊東:ライブでやることのおもしろさって、やっぱり演者と観客が一体になれることにあると思うんです。そこを追求して、舞台と客席を一体化した新しい“イマーシブ(没入型)”な劇空間をつくりたいと思っています。客席は固定でない方がおもしろいし、客席の中にも何か仕掛けを仕込めるような工夫が必要です。
あと、究極的につくってみたいのは、“無目的”ホール(笑)。多目的は無目的だと批判されていますが、じゃあ無目的ホールって何だろう。もう哲学の世界ですよね。
小池:無を極めるということですね。
小林:空間がないということにもなりかねない(笑)。
伊東:それがつくれたらすごいことですよね。極めるというのはそういうことだと思うんです。どんどん削ぎ落として最後に残るのは何か。それを考え続けて、いずれ形にしていきたいと思っています。