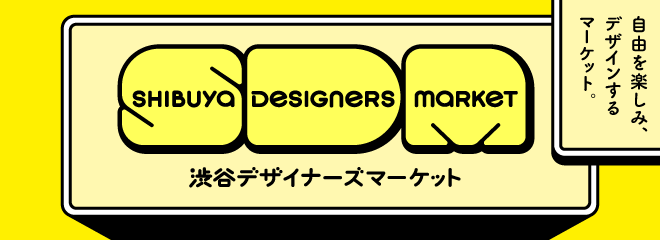ジャーナル
渋谷キャスト7周年祭記念対談「頼まれなくたってやっちゃうことを祝う」のうしろ側

「渋⾕の真ん中で遊び、働き、住む⼈と、これからの街に想像をめぐらせる」そんな街の実験の場として、毎年趣向を凝らした催しが行われてきた渋谷キャストの周年祭ですが、7周年を迎えた今回は今まで以上に挑戦的な内容でした。
持ち寄った自慢の石の魅力を競う「石すもう」や空き瓶片手に規則的な身体表現と吹奏を行う「アキビンオオケストラ」、はたまた「ダジャレ100連発」なども交えつつ、ファッションを双方向の体験に変えるという社会課題へのアプローチも感じさせる「ニューブティック」、さらには『WIRED』日本版 元編集長・若林恵とtofubeatsによるトークセッションなど。
例年にも増してユニークで、若きクリエイターたちが集い、一見不揃いにも見えるこの場がメディアにも注目度高く受け止められた背景には、周年祭を通して渋谷の街づくりまでも見つめ直す、実行委員会の想いがありました。
「周年祭と言っても、何を祝えば良いのだろう?」そんな根本の問いから始まって、創業時のコンセプトのひとつ「不揃いの調和」をすくい上げ、さらには渋谷、東京の街を問うことまで考えたこの特異なお祭りは、いったいどのように形づくられたのか。周年祭ディレクターの熊井晃史さん、主宰の東急株式会社 価値創造グループの丹野暁江さんにお話を伺いました。
「頼まれなくたってやっちゃうこと」に救われた
――4月27〜29日に行われた、渋谷キャストの7周年祭「頼まれなくたってやっちゃうことを祝う」。参加させてもらってあらゆる面で、目からウロコが落ちました。またいただいたブックレットを読んで、これは“これからのプロジェクトをつくる手引書”だと感じました。ものづくりやまちづくりにも通じるかもしれない。既存の評価軸や決まり事にとらわれすぎず、考えることや感じることでの新たな評価軸を生み出していこうという機運を感じたんですよね。
熊井 ありがとうございます。ブックレットには、けっこういろんな思いを込めているんです。何か新しい挑戦を後押しするようなインスピレーションになれば嬉しいですし、イベントをやって終わりにしないためのアーカイブにもしておきたいという気持ちがありました。
一番最初に考えたのは、渋谷キャストという建物の「周年を祝う」という行為が、いったい何を祝うことになるんだろうかということです。そして、それを考えることが、これからのキャストのあるべき姿のみならず、これからの渋谷や都市や文化を考えていくことになるという姿勢を取りたかったんです。
最初は、渋谷キャストが出来上がっていくときに、CMFデザイナーの玉井美由紀さんが提示されて建築デザインコンセプトにもなった、「不揃いの調和」という言葉を祝うということにしたかったんですね。ただ、その気持ちと共に、周年祭が毎年行われるという意味や意義を同時に考えていくと、「不揃いの調和」という解釈のしがいがある言葉を、毎年アプローチを変えていくことによって、その解釈を豊かにしていくという構造にするべきだと思ったんです。
なので、「頼まれなくたってやっちゃうこと」を考えるということは、「不揃いの調和」というものをしっかり考えるための方法でもあったんです。「頼まれなくたってやっちゃうこと」という言葉は、もともとは、グランドレベルの田中元子さんが、過去の周年祭の会議中におっしゃっていたことで、とても印象深かったんです。田中さんからは、記念冊子にも言葉を寄せて頂くことが叶いましたし、そのあたりのこともそこで深掘りしていますので、ぜひ多くの方に読んでもらえたらと願っています。

丹野 4月27日の前夜祭のときに、はじめてブックレットが配られたんですよね。その日の帰り道、なんだかゾクゾクしました。この瞬間に、ブックレットを手にした人たちが読んでいることを想像して、この先起こることを感じ取っていたんだと思います。
実際に「帰りの電車で全部読みました!」とか「すごくよかったです」という感想が続々と寄せられましたね。ブックレットには、読んだ人たちの心に火をつける役割もあるんだと思うんです。

熊井 僕のところにも感想が届いています。 特に若いクリエイターからの声がたくさん寄せられています。今、様々なジレンマを抱えながらものづくりをしている若者が少なくないんですよね。たとえば、大量生産大量消費とも言える社会状況が続いている中で、何かを生み出すという行為が、「ひょっとしたら自分は、ゴミをつくっているんじゃないか」という後ろめたさに紐付きやすいんですよね。そういう後ろめたさを感じながらも、それでもなお、クリエーションに向き合いたい。それこそ「頼まれなくたってやっちゃうこと」に突き進みたいって。
丹野さんが「火をつける」と言うように、実はそんな、特に若い方々の後押しができるといいなと思ってつくった部分もあります。それを前面に出すと押し付けがましくなってしまうし、必ずしもそれだけでもないんで、あくまでも裏側というか、奥のように埋め込んでおきたい意図ではありますけども。

丹野 ブックレット、第2弾も用意しているんですよね。
――え! そうなんですか?
熊井 そうなんです。会期中、写真家に集合写真を撮ってもらうワークショップで撮った写真が沢山ありますし、やってみてどうだったかというところを振り返るのも大切だと思うんで、それをまとめようとしています。題して、『頼まれなくたってやっちゃうことを祝った』。事後に出すブックレットだから過去形に。どうでしょう?
丹野 いいですねえ。

すべてを決めきってしまうところには文化は育たない
――周年祭の中で印象に残ったのが、「アキビンオオケストラ」によるパフォーマンスでした。空き瓶を吹いて音を鳴らしながら、大人たちが突如集合したり、気がついたら長ーい列になって影送りをしていたり。渋谷キャストという公共空間が、一瞬「ここどこ?」という不思議な感覚になったんですよね。公共とパフォーマンスが融合したように見えたというか。
今回の周年祭で「ボキャブラリー(解釈)を増やしていきたい」とお話をされていたお二人に、アキビンオオケストラの見え方についてもお伺いしたいなと。
丹野 アキビンさん、大好きでした! 個人的な話になるんですけど、私は幼少期渋谷で育ったんです。当時はホコ天もあったし、空き地がいっぱいあって「ここを面白いことに使ってやろう」という大人たちが多かった。行政が管理している場所だったので、調整大変だろうなって子どもながらに思っていました……。
熊井 たしかに(笑)。

アキビンオオケストラのパフォーマンスの様子
丹野 路上の使い方1つとっても、渋谷は懐が深い街。文化を下敷きにして、外から来た人たちが創ったのが渋谷という街だと思っています。もちろん地場の人、地元の人も渋谷を創り上げているのだけれど。私の中にはその原風景があるので、渋谷キャストで「見たい風景」のイメージがはっきりあるんです。
アキビンオオケストラの演奏中に、子どもが輪の中に入って遊んでいたでしょう。小さな子も一緒に表現している。まわりにいるみんな、それがこの場を壊さないということがわかっている。あれを観たとき、感動して泣きそうになりました。場を清めてもらった感覚というんでしょうか。祈りに近いものを感じましたね。
熊井 そうそう。アキビンさんたちが演奏しながら輪になってぐるぐる回っている時ですよね。その真ん中に子どもが入っていった。あれはすごい瞬間でしたね。アキビンオオケストラの複数の形式的な動きに、子どもが誘われるようにして入ってしまう。中には子どもが演奏の邪魔をしてしまいそうだからと気を使って下さって止めようとする保護者の方もいるんだけど、そこには「大丈夫ですよ」とフォローするキュレーターやスタッフもいて。俺は、そのギリギリのラインをただ見守っていて。
丹野 私も、ただ見入っていました。

熊井 そう。さらには、この場を運営する東急としてどこまでカバーするかという話にもなってくる。要は、アーティストのパフォーマンスに対して「この線から入ってはいけない」というガイドラインを決めてしまった方が楽なんですよね。リスクは減るから。だけど、それをしてしまうとアキビンオオケストラと子どもとの偶然的なちょっと神がかった状況って生まれづらくなってしまう。
丹野 そこですよね。
熊井 都市開発と似ていて、川の洪水のリスクを減らせば減らすほど、トンボがいなくなってしまったみたいな。なんというか、つまり、そこには明文化できない采配があるんです。たとえば、子どもが演奏中に入ってきて、アンプのつまみをいじろうとしたときは、「ダメだよ」って言う。一方で、パーカッションを一緒に叩いちゃうっていうのは、むしろ微笑ましい。じゃあこれを1つずつ箇条書きにすればいいのかって言うと、そういう訳じゃない。むしろ台無しになってしまう。ある種「文化」としか言いようのないニュアンスを育んでいかなければいけないから、すごく難しいところではあるんですよね。

丹野 「ここから先はダメ」と、線を引くことは簡単です。けれど、運営会社としてそういう方法はとらない。なぜなら、私には渋谷に「見たい風景」があるから。
じゃあどうすればいいんだろう? という部分を熊井さんと長い時間をかけて議論を続けてきました。社内外の人たちに理解をしてもらうために説明も調整も繰り返しました。
渋谷キャストの7周年は、「誰がやっているかがわかること」を重要視して進めてきたように思います。期間中は常に現場にいるようにしましたし、普段から現場やお客さま、地域の方の声をよく聞くようにしています。そういう積み重ねがあったから、リスクヘッジを優先して境界線をつくるようなことをしなくて済んだんじゃないかと。
熊井 曖昧さを積極的に残してそこから価値を生んでいくという意味では、責任を取れる人が現場にいるということの重要性はかなり大きいと思います。
丹野 私は“情熱・パッション人材”なんで!
――その情熱を内側から感じる周年祭でした……!

クリエーションの火を消してしまう言葉
――ここまでお話を伺ってきて、お二人が重ねてきた「言葉」が気になりました。丹野さんは現場の方やお客さま、地域の方との会話を重ねている。それはある意味で、相手に伝わるように「言葉づかいを変換しながらしゃべる」ということなんじゃないかと。熊井さんも、周年祭で「ボキャブラリーを増やす」と繰り返し言っている。お二人は「言葉」をどのように考えていますか?
熊井 うーん。ボキャブラリーを増やしていきたいのも、基本的には考え続けたり問い続けたり、会話をし続ける必要があると思ってのことなんですよね。逆に言うと、それを終わらせるための言葉もある。たとえば、まだ誰も見たこともないことに挑戦をしようよってなっているのに、「それって再現性ありますか?」とか「それってあなただからできるんですよね?」みたいなことを言われると、それは一見正しそうな投げかけではあるんですけど、そこで何かが終わってしまう。
丹野 火がつかなくなっちゃう……。
熊井 そう。っていうか、ライティングもそうでしょ? 火がつかないと書けないじゃないですか。

――まさに。いつも、いかに火をつけるかを試行錯誤しています。
熊井 この周年祭のテーマである「頼まれなくたってやっちゃうこと」っていうのは、実はすごく繊細な言葉で。頼まれたことをそのままやることのほうが楽なんですよね。ある意味考えないで済む。でも、そんなことでいいクリエーションが生まれる訳がなくて、いかに火がつくか、自分がやる必然性を見出せるかっていうことの方が大事。そういう繊細な営みが「頼まれなくたってやっちゃうこと」なわけです。
「再現性あるんですか?」という問いを放り込む前に、そもそも、それを再現したくなったのかどうか、再現したくなるほどのものを生み出せたのかどうかを問うべきだと思います。でも、そこのそもそもの会話が育まれないままに、せっかく着きそうな火が消されてしまうなんてことは溢れていると思います。
言葉を大切にするということは、人を大切にするということとほとんど一緒だと思うんですね。だからこそ、言葉づかいが変われば、人間関係も変わるし、人間関係が変われば行動も変わる。そして、行動するから成果が変わるんです。

丹野 そうなんですよね。私はこういう仕事のやり方しかわからないからなあ。やれることは全部やってきたっていうのはありますね。
会社と私のことを少し話すと、東急文化会館や文化村があったり、百貨店があったりと、幼少期から文化的なことを東急を通して体感していて。そして今、「美しい時代へ」※ っていうコピーがあるんですけど、新しいことに挑戦するとか、これまでにない考えを受け入れることには寛容な会社なんだなって、子ども心に感じていたことが、今も会社のスローガンとして継続している。文化をつくろうとしているんだって。
何より「美しい時代へ」だなんて! とてもとても「美しい」と感じちゃう。
熊井 なるほど。
丹野 中途採用で東急に入って数年経ちますが、実は私、前々職でもこの渋谷キャストに携わっていまして。劇場コンサルの会社だったんですが、その時にこの施設の話があがりました。当時私は十数年渋谷に住みながら、このエリアがもう何年……十何年ってくらい少し長い期間停滞しているな、って感じていたんです。パルコさんが閉まり、建て替わるまで時間もかかっていたりと。駅から上ってきて代々木公園へ繋がる公園通りが少し暗い感じになっちゃっていて。ちょっと入った裏通りとかは、地道に頑張っている方々、沢山いましたけどね。
でも、以前の渋谷とは違う印象を感じながら暮らしていたので、東急がこの場所に、渋谷で「遊ぶ、働く、住む」複合施設をつくりますっていうのを聞いて、すごくいいな!って思ったんです。なんか、そこに東急の本気、というか素敵な心意気を感じて、ワクワクしちゃった。あれ? これなんじゃない?って。
プロジェクトの参加者が募られたときに、「やります!」って社内で手をあげました。これまでの仕事でやったことのないような踏み込んだ内容だとも感じました。準備室時代は運営からは私1人しか人員は割けなくて、開発の1年前から1人で営業をしながら、仲間を募りつつやってきました。それこそずっと「頼まれなくたってやっちゃうこと」をやって、この場所に携わってきたんです。そういえば、ですけどね。

――すごいストーリー。キャストには丹野さんの人生が反映されているんですね。
※ 東急グループのスローガン。
人間が人間同士であることを回復させるために
――お二人はずーっと「文化」をつくっているんですね。いろんな解釈ができる理由が見えてきた気がします。
丹野 大きい話ですが「人間という動物」には、文化が必要不可欠だと思うんです。文化がなくなったら、とんでもないことになるという、危機感もちょっとあるんです。文化が生まれることで想像力が富み、人を優しく思いやれるんじゃないかと、本気で考える時があります。考えることや感じることを、いつまでも放棄したくない。
熊井 僕は教育の仕事をずっとやっているんですけど、教育の定義はまちまちに色々とあるんですけど、基本的には文化なるものに参画していくことが学びであるように考えています。そういえば、「生涯学習」という言葉がありますよね。今の日本では、この言葉を聞いてもワクワクする人はほとんどいないと思うんですけど、この言葉を提唱していたポール・ラングランというフランス人の原著を読んで、結構ワクワクしまして。ラングランって、ナチスのレジスタンスをやっていたような人なんですが、その経験を経て、戦後のユネスコで生涯学習というコンセプトを提唱していたいですね。

丹野 それでそれで?
熊井 原著には結構なパンチラインがいっぱい出てくるんです。今の丹野さんのお話にもつながってくるんですよ。彼にとって、生涯学習とは「人間が人間同士であることを回復すること」。更に「生涯学習を生涯学習たらしめるためには、教育者は都市開発者や都市計画家、建築家と共創しなければならない」みたいなことを言ってるんですね。
これはつまり、教育っていうのは学校だけじゃなくて、街や社会において「あんな人になってみたいな」って憧れを生んだり、いきなり空き瓶吹いてる人を見て感動するとか、偶然の出会いや意外性をひっくるめたことを言っていて、それを都市開発と紐づけているんです。そこでは思わず学んじゃってたみたいな、偶然性や非意図的なものも肯定されているんです。
丹野 なるほどなあ。私たちみたいだ。
熊井 そうそう。もう少し素直に言っちゃうと、今回の周年祭において、丹野さんの言葉を残しておきたいと強く思っていたんですよ。ただ、渋谷や東急という大きな主語を背負った状態というか、そういう風にどうしても見られる宿命のある人の腹から出ている言葉というものを、どのように社会に置いておくのか、という所は結構繊細な話になってくるなと思っていて、そこは丁寧にやっていきたいとは考えていました。

――よくわかります。
熊井 だからまず、人間同士であることを回復させていく。そうしないと、大企業対クリエイターみたいな対立構造になってしまう。でも、それで世の中が前進するのかっていうと、そうじゃないでしょう。だから、「人間同士の会話しませんか?」っていうところからしか、事態は良くなっていかないと思うんですよね。
――丹野さんがこれまで渋谷キャストの周辺で続けてきた、様々な方々との会話も「人間同士の会話」ですもんね。
(突如、「ワン!ワン!」と犬の鳴き声が響く)
丹野 あ、ちょっとごめんなさい。……はい、丹野です。
――丹野さんの着信音、犬の鳴き声なんですね。動物好きだとは聞いていましたが、ここまでとは!
丹野 (電話を終えて)他の着信音だと気づかないんですよね(笑)。
熊井 ほんとはそういう話だけし続けたくもあるんです。

PROFILE
熊井晃史さん(くまい・あきふみ)10代向けの学び舎「GAKU」事務局長、ギャラリー「とをが」主宰。子どもたちの創造性を育むワークショップ等を普及するNPO法人「CANVAS」プロデューサーなどを経て2017年に独立。以後も一貫して子どもたちの創造性教育の現場に携わる。2021年に社会教育の可能性を探る書籍「公民館のしあさって」(ボーダーインク)を編集発行。
丹野暁江さん(たんの・あきえ)渋谷キャスト7周年祭・統括/東急株式会社価値創造グループ文化用途企画運営担当。「頼まれなくたってやっちゃう」の精神で渋谷キャストの立ち上げに携わり、2019年11月より現職。渋谷ストリーム専任からスタートし、これまでに北谷公園の兼任を経て現在は渋谷ストリームと渋谷キャストを兼任。
CREDIT
執筆:山本梓
撮影:須藤翔(Camp Inc.)
編集:横田大、須藤翔(Camp Inc.)