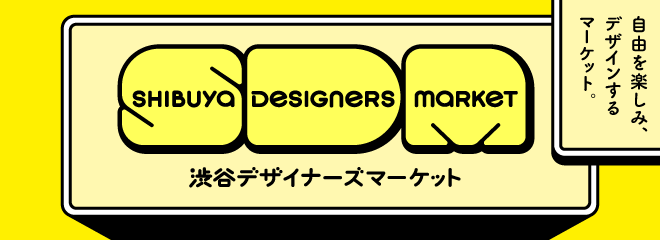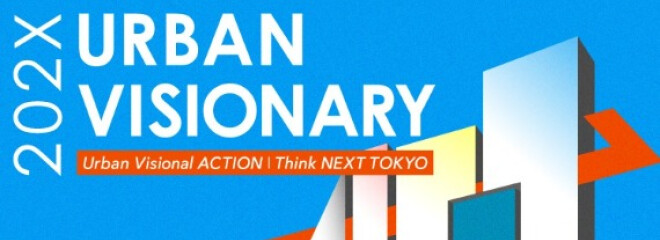ジャーナル
120%手づくりの創造性。「みんな」に光が当たる、渋谷キャストの8周年

2025年4月28日(月)に開業8周年を迎えた複合施設「渋谷キャスト」。渋谷・原宿・青山の交差点に位置しながらも、渋谷の喧騒とは少し異なる落ち着いた居心地と、地域に開いたイベントづくりで近隣住民の方々からも愛されてきました。
今回のジャーナルでは、そんな渋谷キャストの8周年を記念して催されたイベント「つながるフェス。『渋谷キャスト8周年祭』」の様子をレポート。多種多様なゲストを巻き込んできたこれまでとは打って変わって、「キャストの入居者たちでつくる」ことにこだわったという今回の周年イベントには、多様な人々の「住む」「働く」「暮らす」を支えてきた渋谷キャストならではのお祭りの様子がありました。
多くの人が行き交う渋谷・原宿・青山の交差点にありながら商業施設ではない。かといってオフィスに注力するでもなく、住居やスーパー、ひと息つけるカフェなど、さまざまな施設が手を取りながら軒を寄せ合っている——そんな渋谷キャストならでは魅力とは何なのか。周年の度チャレンジしてきたその問いをひもとくヒントは、ここを居場所に選んでくれた魅力的な“キャストたち”にあるのではないか? そんな仮説のもと、彼らの創造性が引き出された2日間の様子をレポートします。
<開催概要>
2025年4月25日(金)・26日(土)
「渋谷キャスト8周年祭」
主催:渋谷キャスト(東急)
コンテンツ企画・運営:Moment Factory、WAT、春蒔プロジェクト、デジタルハリウッドstudio渋谷、Cift
クリエイティブディレクション:春蒔プロジェクト
クリエイティブ制作
キービジュアル・デザイン:hooop
コピー・ステートメント:YABCOPY 藪内一真
企画運営・支援:シアターワークショップ
「外」から「中」へ。視点を戻すことでこの場所の価値を見つめ直した

商業施設でもなければオフィスビルでもない、機能はあるけど集合住宅と呼ぶのもすこし違う。でも、「住む、働く、遊ぶ」ための機能はすべて持ち合わせている。「渋谷キャストってどんな場所なの?」と聞かれると、一言で伝えるのは難しいというのが正直なところ。だからこそ、渋谷キャストは周年祭に限らず、これまでさまざまなイベントを開催し、集まってくれた人々とともに「この場所はいったい何なのか?」を自ら考え続けてきました。
渋谷に訪れた人と“渋谷が地元の人”が混ざって営まれる恒例の盆踊りイベント「BON CAST.」や、渋谷キャストのコンセプト「Share The Creative Life」に基づいてつくり手と来場者が共に創造性を発揮していく「渋谷デザイナーズマーケット」、ほかにも近隣で暮らす人々が仲良くなることを目的とした渋谷区主催のイベント「渋谷おとなりサンデー」への参加など。その多くの取り組みは、より多くの人々と渋谷キャストの価値について考える きっかけを生み、地域や利用者との深いつながりを育んできました。
 2017年に初開催された盆踊り大会「BON CAST.」には、クリエイター、住人、オフィスワーカー、地域の人が大集合した
2017年に初開催された盆踊り大会「BON CAST.」には、クリエイター、住人、オフィスワーカー、地域の人が大集合した
 毎年恒例のイベントとなった「渋谷デザイナーズマーケット」
毎年恒例のイベントとなった「渋谷デザイナーズマーケット」
たくさんの方の力を借りて開催してきた周年祭も、今年で8回目。これまでの周年祭は渋谷キャストが築いてきたつながりを地域や周辺の方々に還元するためにも、「都市」や「公共」を テーマに、外部パートナーとの協業をメインにつくりあげてきました。 しかし 2025年は、渋谷キャストが自問し続けてきた「この場所はいったい何なのか?」という問いと向き合うためにも、つながりをつくりあげてきた大元である「渋谷キャストの内部」に視点を戻すことに 。この場所に入居している多彩な方々が主役となり、「キャストの中の人といっしょにつくる」ことに徹底的にこだわったお祭りになりました。
渋谷キャストのコンテンツ企画を手がける東急株式会社 不動産運用事業部 価値創造グループの高木顕一郎さんは、今回の周年祭について「キャスト100%でつくりきったイベントになった」と振り返ります。

「渋谷キャストが特徴的なのは、渋谷・青山・原宿の文化が混ざり合うちょうど中間くらいのエリアにありながら、商業施設ではないというところです。オフィスがあって、店舗があって、上には住居があり実際に暮らしている人がいる。遊びに来てくれる人の数と同じくらい、実は、毎日ここで働いたり暮らしたりしている人がたくさんいる。その不思議なバランスがあるからこその場所の魅力もある。そんな複雑な魅力を示せるイベントになればと考えました」。
クリエイターコミュニティが暮らす居住区があったり、複数の企業がオフィスを構えていたりと、入居者は多様で多彩。「タレント性のある方々が入居し、共に運営している施設なんです。だからこそ、本人たちのクリエイティビティを存分に引き出しつつ、『みんなで2〜3歩ずつ、ちょっとだけ無理をしてみませんか?』とお願いをしました」と笑いながら話す高木さん。
「キャストに関わることで、創造性が引き出され、育まれる施設であるということを目指しています。クリエイティブとは、自分たちに出来る範囲よりも少し踏み越えて表現することじゃないか? と話したところ、入居者の方々も共感していただけたんです」。
「原点に戻って、ここにいる人たちの魅力を伝えたい」高木さんのそんな思いは、入居者たちが用意した2日間のコンテンツに現れていました。
街に開かれた、カフェが育んだ出会いとつながり「Marked Market」
周年祭が開催された4月25日〜26日の2日間、渋谷キャストのガーデン(広場)で訪れた人たちをまず出迎えてくれたのは、1階に入居するカフェ「Marked」が企画した「Marked Market」。この日のために、15店舗もの出店と角打ちブース、軽トラDJにフードトラック、ワークショップエリアなど多くの出店者が広場に集結しました。

Markedは、“よい人のつくる、よいもの”を届けるコミュニティカフェ&マーケット。マルシェにも、いいものづくりの背景に確かな理由と物語がある商品やアイテムが勢揃いしました。

お米屋さんの2代目が「お米のおいしさを残しつなげたい」と開発した新しいポン菓子ブランド「PON」を携えて出店してくれた、KURISAKI SHOTENさん
 大分県・耶馬溪の自然に囲まれたレストランサルディナスの人気商品「レモングラスオイル」は、Markedのお店でも販売する一押しの食品です
大分県・耶馬溪の自然に囲まれたレストランサルディナスの人気商品「レモングラスオイル」は、Markedのお店でも販売する一押しの食品です

当のMarkedはフードトラックとして広場に登場。美味しいカレーやお弁当で来場者のおなかを満たしてくれます

キャスト前の広場いっぱいを埋め尽くす、ストーリーのある製品と出店者さんたち。充実したマルシェをつくりあげた「Marked」でしたが、実はマルシェを自主企画するのは初めての試みだったといいます。「やってみないとわからない部分ばかりだった」と言いながらも、2歩、3歩と踏み込んだクオリティ高いマルシェを実現していました。
「はじめてのマルシェで、どうしてここまでの大規模な催しを実現できたんでしょう?」Markedスタッフの吉武さんは「これまでの生産者さんとのつながりがあったから」と答えてくれました。
生産者の方や近隣の方との関係づくりを大切にしているMarkedさん。マーケットに出店していた、石鹸ブランドのmueさんやハンドメイドアクセサリーのfunifさんは、過去に開催したワークショップに出てくれた方々。ふだんお店で提供しているアイスクリームに使っているいちごの生産者である美岳小屋さんも、今回はるばる愛知から出店してくれたのだといいます。
 1つ1つ手づくりで植物オイルをベースにしたせっけんを制作するブランド「mue」さん。天然石のようなビジュアルと美しいディスプレイに多くの人が足を止めていました
1つ1つ手づくりで植物オイルをベースにしたせっけんを制作するブランド「mue」さん。天然石のようなビジュアルと美しいディスプレイに多くの人が足を止めていました

愛知県豊橋市とみよし町で、生命力に溢れるいちご栽培を行っている「美岳小屋」さん。野外販売で提供できる季節は、いま(4月末)が最後だと、愛知から駆けつけてくれました
Markedスタッフのみなさんのお店を営むなかで生まれたさまざまなつながりが、マルシェというかたちで広場に立ち上がっていました。

そして会場では、日中からカクテルやワインを楽しむ人たちが。ナチュラルワインを中心に外で飲みたくなるお酒を取り揃えたワインバーや、千葉県にある薬草園蒸留所「mitosaya」のオー・ド・ヴィー、ボトリングファクトリー「CAN-PANY」が提供する炭酸飲料など、さまざまなドリンクが、会場の人々を楽しませ、広場でゆっくりと過ごす時間のおともになってくれていました。

mitosayaのオー・ド・ヴィーとCAN-PANYの炭酸飲料をブレンドしたカクテルも提供
お買い物をしたり、おいしいドリンクを飲んだり、お酒を片手に友人たちとおしゃべりをしたり。情報と人の流れのあまりに早い渋谷・原宿エリアにいることを忘れるほどに、広場には穏やかな時間が流れていました。
さらにマーケットには、買い物や飲食だけではなくMarkedならではのものづくりが体験できるワークショップコーナーも。 ひときわ目を引いたのは、美しく咲いているガーデニングコーナーの花々でした。

Markedで使われていた荷物カゴをプランターへとリメイクし、「周年祭の間にみんなでつくっていく花壇」へと変えたこの企画。訪れた近隣の住人や、渋谷キャストのオフィスフロアで働く人々、休日に遊びに訪れた若者まで、多くの人が思い思いの花を植えてくれたそう。

イベントの最中に、施設の風景が美しく変わっていく。「みんなでつくる」という渋谷キャストの思いが、ここにも現れているようでした。
現実と創造性を拡張するデジタルアート「Moment Factory」
表から見える場所だけじゃないのが、渋谷キャストのおもしろいところ。8周年というこの節目に、入居しているクリエイターや企業もまた自身のクリエイティビティを発揮し、この場所を盛り上げるコンテンツを提供してくれました。

大階段の脇からスペース(多目的ホール)に入ると、薄明かりの中に光る大きなモニターやフォトブースが。渋谷キャスト co-lab内に東京オフィスを構える複合エンターテイメントスタジオ「Moment Factory」は、AI技術を活用した最先端のフォトブースと、老若男女が楽しめるお絵描きゲーム体験を提供してくれました。
「Monster Sketch Game(ゲーム体験)」では、設置された端末に来場者が手書きで描いたイラストをAIが読み込み、モニター上に新たな生き物(モンスター)を生成。実際に自分が描いたお絵描きに命が吹き込まれ、画面上でモンスターになっていく様子を見た来場者はみなさん驚きの声をあげていました。
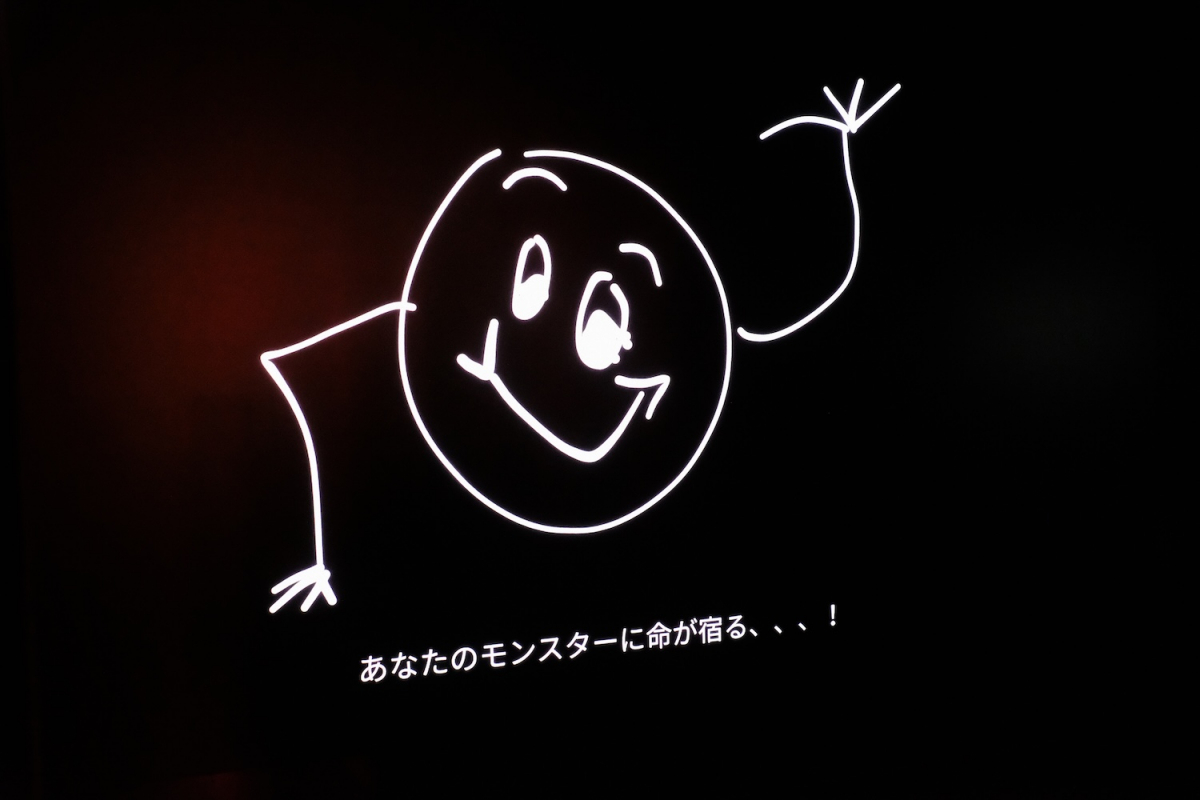

体験者が描いたイラストを読み込み、世界観のあるモンスターの姿形へと生成される

子どもから大人まで、たくさんの人が並んでは、自分のモンスターをAIに生成してもらう体験を楽しんでいました
入り口近くにあるフォトブースのテーマは「春の芽吹」。タッチパネルを操作して写真を撮ると、AIが春らしい幻想的な自然やファッションを生成し、体験者一人ひとりの自己表現を新たに描き出します。
 AIが変換する自身の写真に驚いたり笑ったり。年齢を問わず、多くの方がフォトブースに夢中になっていました
AIが変換する自身の写真に驚いたり笑ったり。年齢を問わず、多くの方がフォトブースに夢中になっていました
「実は、渋谷キャストのイベントに参加させていただくのは今回がはじめてなんです」
そう語ってくれたのは今回のブースでコーディネーターを担当された浅谷さん。そもそも周年祭を含む多くのイベントが土日開催ということもあり、渋谷キャストを「職場」とするMoment Factoryのメンバーはなかなかイベントに遊びにくることもできていなかったそう。「どうしたら渋谷キャストという会場の持ち味を最大限に活かせるか」という問いと向き合いながら生まれた2つの企画は、Moment Factoryにとって、はじめて渋谷キャストと“職場以上”の繋がりとして協業することで生まれた作品になりました。
ただ明治通りや広場を通り過ぎるだけでは、決して知るよしもなかったであろうAIによるクリエイションとデジタルアート体験。それは、渋谷キャストの中で日々育まれている創造性が、入居者たちの協力によって多くの人へと開かれた時間でした。
「話したい!」熱量を持ち寄る、Energy Design Hub
8周年祭初日の夜には、大人たちが自由にアイデアを持ち寄り発散するトークライブ型のイベントも。クリエイター向けコワーキングスペースco-lab渋谷キャストの会員である4CYCLEの田井中慎氏が、co-lab渋谷キャストとともに開催したイベント「ENERGY DESIGN HUB TALK LIVE」では、「Stairs(階段)」をテーマに写真スライドを用いて登壇者それぞれが考える「エナジー」についてのトークを展開しました。
メインとなるコーナーには、近隣の神社で宮司を務める方や、長野県で林業を営む方、大学教授や中学校・高等学校の副校長など、業界やジャンルを越えた10人のゲストが登壇。事前に各々が持ち寄った写真がランダムで表示されると、その場でその登壇者にマイクが手渡され、1人60秒の制限時間のなかで走り抜けるようにアイデアを共有します。生きものにも見える巨大な茂みを見せながら、植物のエネルギーについて語る方や、テーマ通り神社の「階段」を見せながら、その場所の歴史について思いを馳せる方など、内容はさまざま。登壇者と参加者が混じり合いながら次々とアイデアが飛び交う、エキサイティングなトークライブになりました。

人が集まって話すことこそ、身近にある「エナジー」だと語る田井中さん。さまざまなバッググラウンドを持つ人々が日々の発見ややりたいことをインタラクティブに参加者と共有することで、その場に居合わせた人たちのなかにも、渋谷のまちとの関わり方について新しい⼀段を踏み出すエナジーが生まれていました。

また、トークライブの直前には、渋谷キャスト内にある「co-lab渋谷キャスト」の見学会も開催。クリエイターを支援する機能があり、コラボレーションの起きやすい環境が整備された共用部や専有オフィスといった場所を訪れ、渋谷キャストを拠点に活動することのイメージを見学者の方々と共有しました。
「自分らしさ」を叶えるための学びの場
渋谷キャストは働く場所であると同時に、社会人に向けた「学びの場」も内包しています。施設内にあるデジタルハリウッドSTUDIO渋谷では、Webデザインやグラフィックデザイン、動画制作などの講座を開講し、柔軟な時間とカリキュラムを通して実践的なスキルを学ぶことができます。

そんなデジタルハリウッドSTUDIO渋谷さん、周年祭では「自分らしい働き方を叶える セルフブランディング講座」と題し、自分を理解するためのワークショップと講座を開講していました。「自分の個性や強みは何か」「やりたい仕事を実現するにはどう考えればいいのか」などにまつわる講義ののち、講師をまじえたワークショップで、自己理解と実践をつなげるための対話を重ねます。

社会に出てある程度年齢を重ねると、やりたいことを自分で見つけ、それを学ぶための場も自分自身で獲得しなければならないことが多くなります。自己を振り返って言語化するワークショップに参加したみなさんは、そのための第一歩を踏み出していきました。
「家族と思ってみた」人たちとのファミリーディナー
渋谷キャストの上層階には、クリエイターたちが集まる居住区があります。「Cift」と呼ばれるそのエリアでは、「拡張家族」という考え方を共有し、その価値観に共感した人々が集まって新しいコミュニティが生まれています。

周年祭では、そんな「Cift」への入居を検討している方々に向けて、実際の居住スペースで「説明会」と「ご飯会」を兼ねたイベントを開催。
入居者の石山アンジュさんは、Ciftのコミュニティについて「『相手を家族だと思ってみる』ということからはじまる、意識の社会実験だと思います」と語ります。さまざまなバックグラウンドを持った人たちが支え合いながら、ときにいろいろなものを共有しながら、自分ごととして捉えられる生活の範囲を拡張していく。
間取りの違う部屋が20室ほど並ぶ1フロアのなかで、みんなで部屋を行き来したり、食事をいっしょにしたり、ここで暮らす子どもたちが、誰かの部屋に集まってゲームで遊んだりすることも。「地域での見守り」や「友人のお家へお出かけ」といった普通を超えて、ただ当たり前に「いっしょにいる」風景がそこにあるのだそう。
Ciftのみなさんは口々に「新しい家族の定義をつくるのではなく、『家族ってなんだろう』という問いを持ちながら、自分たちなりの暮らしをつくっていく」そんなコミュニティなのだと言います。
説明会のなかでは関心を持って訪れた見学者にもマイクが渡り、自分の話をとつとつと話すシーンも。どんな暮らし方が理想なのか? どういう家を求めているのか? そんな考えについて、入居者と見学者が互いの考え方を渡し合いながら、この場所の空気を知っていく時間になりました。

対話が続くなか、隣にあるキッチンでは早々に夕飯の準備が進んでいきます。食卓を囲みながら話すほうが、お互いにわかることがあるだろうと、食事会のかたちをなして対話が行われていきました。

食事とともにお互いのことを話し、Ciftの暮らしの特徴について肩ひじはらずに話す。お客さん向けに開かれた場のようでいて、これに似た対話の時間は日々ここにあるのだろうと推測できる時間でした。
「ここに来れば、みんなキャスト」
個性豊かな入居者を中心に実現した、渋谷キャスト8周年祭。
冒頭でこの8周年祭を「エゴ100%でつくった」と語ってくれた東急の高木さんは、「今回の周年祭を通して、入居者をはじめいろいろな方との関係性をつくり直すことができた」と話します。
渋谷キャストからの呼びかけに応えてくれた入居者の創造性が、それぞれに発露した今回。マルシェ初開催のMarkedはこれまで培った関係性を広場のにぎわいに変え、Moment Factoryは開発していた技術を実装したプロトタイプを今回のイベントのために広く一般の人々が触れるかたちに仕上げてくれました。
そして忘れてはいけないのが、イベントのビジュアルやコピーをはじめとしたクリエイティブの数々。渋谷キャストの外観をデザインに取り込みながら、人々が交流する様子を表現したメインビジュアルは、co-labを運営する春蒔プロジェクトさんが指揮を取り、co-lab渋谷キャストに入居しているhooopさんがデザインを、コピーライターの藪内一真さんがコピーを担当しました。ふだんはco-labでそれぞれの仕事に向き合うクリエイターたちが、このイベントをきっかけに共作した作品です。
 当日は各会場でもらえるシールをパンフレットに貼ることで景品がもらえる「シールラリー」も開催された
当日は各会場でもらえるシールをパンフレットに貼ることで景品がもらえる「シールラリー」も開催された
「こうしたそれぞれの自由な創造性から生まれるにぎわいは、商業施設からは生まれづらいものなんじゃないかと思うんです」。
クリエイティブなこと、クリエイターたちの存在をたいせつにする場所でありながら、誰かを置いてきぼりにしない。キャストを訪れ関わってくれた人たちがそれぞれに新しい発見や気づきを持ち、また違うかたちで関わりたいと願う。そんな場所を目指しているんです、と高木さんは言います。
住む人も、働く人も、遊びに来る人も、運営する人も、この場所を通してどこかでつながっている。社員証を首に下げたまま広場でお買い物をする人や、入居企業のコンテンツに触れて楽しむ家族連れの方々を見ていると、意識せず当たり前にゆるいつながりが生まれていることを感じます。渋谷キャストという土壌が、場や人に「関わる」ことの喜びを当たり前のものにしてくれているのかもしれません。
「顔のある関係性があることで仕事につながったり、住む人やいろんなかたちでキャストに訪れる人の日々の暮らしが良くなったり。渋谷キャストは、この場に意思があるように、そういう場所になっていきたいんです」と高木さん。
一人ひとりに違った関わり方があって、この場所はそれを受け入れてくれる。co-lab渋谷キャストの入居者のひとりである藪内一真さんが考え、言葉にしたコピーは、8年かけて渋谷キャストが培ってきた性質をピタリと言い当てているように思いました。
「ここに来れば、みんなキャスト。」
集まるみんなにスポットライトが当たり、誰もが演者に、そして楽しむ人になれるこの場所は、これからも集まる人たちによってかたちづくられていくのだと思います。

CREDIT
執筆:乾隼人
撮影:須藤翔、Re!na(Camp Inc.)
編集:横田大、須藤翔(Camp Inc.)
デザイン:山下舞、植木駿(Camp Inc.)